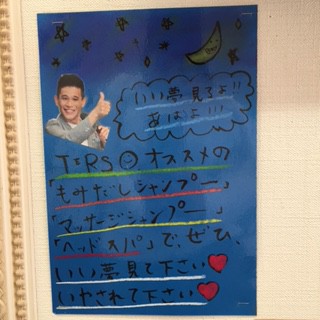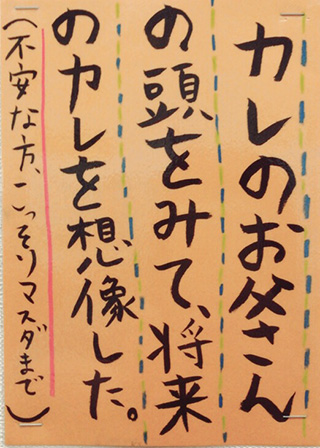こんにちはマスダです♪
先日のアカサコくんのblogにもありました
ロコルっていう名のカラー剤。
トリートメントカラーとも言われてて
淡?い色から、ビビットな色まで
トリートメントしながらカラー出来る
っていう優れもの(^_^)☆
先日営業後セミナーに行ってきましたが、
1人目のモデルさんは
あまり見れませんでしたが、
アッシュにしたーい!
でも赤みが邪魔をするー(´・_・`)
って方向けの手法。
2人目のモデルさんは、
ハイトーン。
根元は新生毛、
中間はブリーチ
毛先もブリーチ×2くらい?
の髪質でございました。

ここから目指す色はターコイズブルー。
緑なのか、青なのか。

なかなかなビジュアル。笑

仕上がりはこちらー!

個性的なカラーをしたい、
そんな方にはもってこいです!笑
ベースをしっかりと作ってしまえば
可愛いカラーが出来るし、
トリートメント効果あるし、
一石二鳥。
今日お店でも使ってみましたが、
(ペールアッシュの方♪)
いやー、ブリーチして
赤みが邪魔してた部分に乗せるだけで、
自然なアッシュに♪
本当トリートメント感覚のカラーなので
放置時間も10分くらい(^_^)☆
マスダもしてみたいなー笑
皆さんもオススメなのでぜひ(≧∇≦)